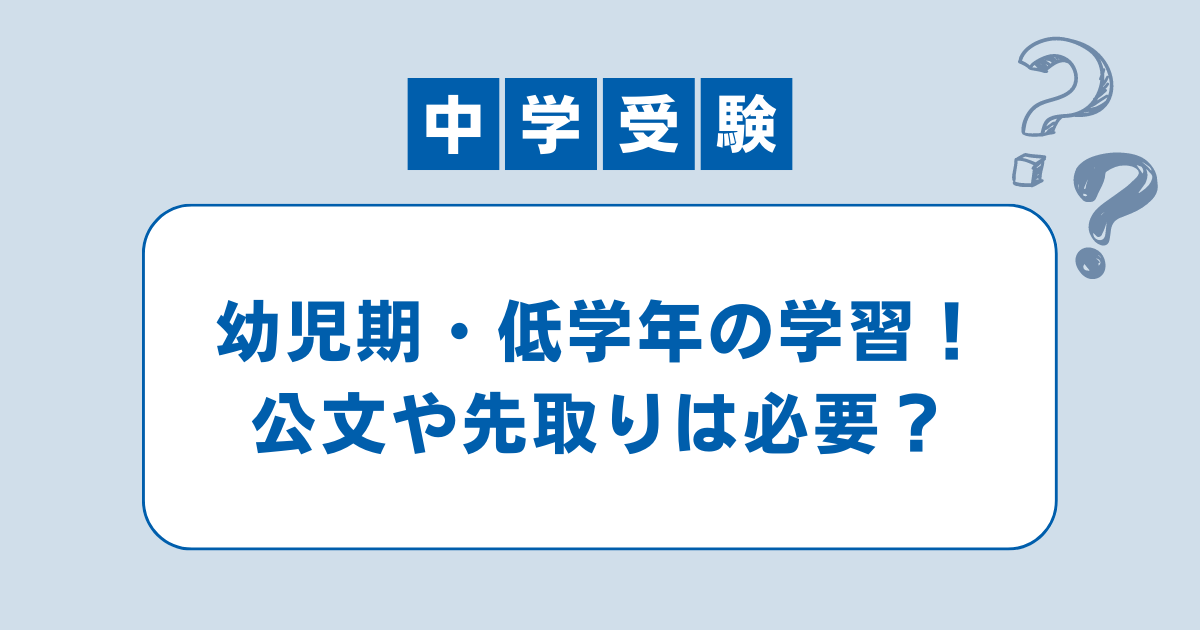
中学受験を考え始めたらまず何からすればいいのか、4年生で入塾するまで何をしたらいいの?
よく4年生で中学受験の塾に入るまでに、公文で小学校の教材を終わらせた方がいいとか、御三家を目指すなら算数は中学教材のHの連立方程式までやっておいた方がいい、
といった話を聞きます。
今回の記事では、我が家が幼児期から低学年で目安として設定して取り組んだこと、入塾までにやってよかったこと、ここまではやらなくてもよかったと思ったことをまとめて記事にしたいと思います。
公文
まずは王道の公文式。中学受験を目指すなら塾の新4年生のカリキュラムが始まる3年生の2月までに国語算数ともに公文のF教材の四則演算まで終わらせるといいと言われています。
我が家も実際に幼稚園の年長から公文式を始め、入塾するまでに(息子の場合は、新3年生のタイミングで入塾しました)国語はF教材まで終了、算数はH教材の連立方程式まで進みました。当初は4年生まで公文は続ける予定でしたが、思いのほか進みすぎてしまったため、これ以上公文で先取りをしても意味がないかなと思い通塾に切り替えました。
公文をやっていてよかった?
公文の教材は、中学受験の内容とは全く異なります。国語は、ひたすら文章を読んで、大切な部分を抜きだす。算数は、文章問題はなく計算のみで、中学受験の勉強には直結しません。逆にいうと、公文でいくら進度がよくても中学受験の勉強ができるとは限りません。
国語は色んな種類の文章をたくさん読むことができたので、自分の興味のある本しか読まない息子にとってはよかったです。
算数は公文をやっていたおかげで計算が速く、問題を解くときにその分他の問題に時間を使うことができました。
算数のF教材の四則演算までは、やっておいて損はないと思います。でもそこまで行くのが難しい場合、E教材の分数の最初くらいまでやっておけば、あとは塾で習うので無理する必要はないと思います。
御三家を目指すならH教材の連立方程式までやった方がいいかという点ですが、負担なくそこまで進めるならやっておいてもいいかなくらいだと思います。
中学受験の単元でも連立方程式のような消去算というものを習うので、その時にしっかり学習すれば問題ないかと。結局、先取りしても反復し続けなければすぐに忘れてしまうので。
公文は勉強する習慣をつけるということと、基礎を徹底的に身に付ける点では公文はとても役に立ちました。息子曰く、学校の勉強も公文のおかげで簡単で自信につながったそう。
最レベ・トップクラス問題集・スーパーエリート問題集、ハイレべ100・きらめき算数脳
御三家などの難関中学を目指す場合、公文だけでは文章問題や図形、パズルなどの問題を取り扱わないため、最レベ、トップクラス問題集、スーパーエリート問題集、ハイレべ100、きらめき算数脳などの問題集で受験算数の先取り学習をするのがスタンダードとされています。
これらの問題集ほとんど試しましたが、正直、無理にやらなくてもいいかなというのが率直な感想です。
特にスーパーエリート問題集やトップクラス問題集の算数は、受験算数を低学年用に無理に難しくして作っているだけなので、低学年の段階で解ける必要はないと思います。
息子は小学校2、3年生の頃、トップクラス問題集の算数には拒絶反応を示していましたが、通塾しはじめてからは、算数は得意科目で、6年時には灘や開成、聖光の算数も解けるようになったので、低学年の時点で解けなくても心配する必要はないと思います。逆に低学年の段階でそのような問題が解けても、それが高学年まで続くとも限らないので…
4年生からのカリキュラムが始まってからきちんと基本を学習していくことの方が重要だと思います。
最レベも上記の二つよりは難易度は低いですが、問題集自体が分厚くて、低学年には書き込みにくいので使い辛いです。
この中で我が家が使ってよかったのは、ハイレべ100ときらめき算数脳です。
ハイレべ100は難易度もほどほどでプリント形式で使いやすいので、これは国語・算数ともにおすすめです。なかには難しい問題もあるので、できる問題だけで十分だと思います。
きらめき算数脳はSAPIXが出している教材でパズルや回転図形等、小学校受験のペーパーテストに似た感じの問題集です。これは思考力を鍛える問題集で、キャラクターがでてきてゲーム感覚で楽しくできるのでおすすめです。
学習漫画で楽しく学ぶ
息子が通っていた公文式の教室の待合室にたくさん本が置いてあり、学習が終わってから私が迎に行くまでそこで本を読んで待っていることがよくありました。その時に公文の学習漫画を笑いながら楽しそうに読んでいて。
それ以来、息子が好きなドラえもんやちびまる子ちゃん、コナンくんの学習漫画を買って、お出かけの時や待ち時間がある時に持ち歩いてよく読んでいました。
学習漫画だけど、普通に面白くて笑ってしまうので、普通のマンガとしても楽しめます!シリーズで色んな教科や単元があって、興味のあるものを楽しく学べるのでおすすめです。
ゲームでも学べる
息子は小さい頃から電車が好きで、よく図書館で電車の本や路線図などを読んだり眺めたり(首都圏のポケット路線図をお出かけの時に持ち歩いてた)していたので、日本の地理や地名などには詳しかったのですが、ゲームの任天堂Switchの「桃太郎電鉄」でも日本地図や地名、特産物などを覚えられるのでおすすめです!
小学生になると、ゲームゲームとなりがちですが、楽しめて勉強にもなるゲームもあるので、うまく活用するといいのではないかと思います。
好きなことや興味のあることを伸ばす
中学受験の勉強には関係なくても興味のあることを伸ばせる環境を作るようにしました。
電車が好きだったので、長期休みには新幹線を見に行ったり、鉄道博物館に行ったり。
週末にパパと路線図を広げて予算を決めて、今日はここのルートでどこどこまで行ってみよう!と電車の旅に出かけたり。
宇宙や天体にも興味があったので、科学館や博物館、プラネタリウムに行ったり。
三鷹の国立天文台の天体観測のイベントに参加したり、月食などに時は空を観察したり。
NHKの「コズミックフロント」や「サイエンスゼロ」「地学基礎」なんかは録画して暇な時によく見ていました。
通塾が始まって、5年生6年生になると時間が取れなくなるので、低学年のうちにいろんなところに出かけたり体験するといいと思います。
まとめ
今回の記事では、中学受験を考え始めた幼稚園の年長から低学年の学習でやってきたこととやってよかったことをまとめました。
低学年のうちはあまり先取り先取りと前のめりにならず、基礎をしっかりと固めて勉強の習慣をつけることができればいいのではないかと思います。
公文に通っていなくてもお家で計算ドリルを買って解くのでも、スマイルゼミ ![]() や進研ゼミでもいいと思います。
や進研ゼミでもいいと思います。
また、日々の生活の中で興味のあることを楽しみながら学んで知識の土台を作り、種まきをすることが大切だと思います。
そうすることで実際に高学年になって中学受験の勉強を始めた時に、知識が広がり勉強が楽しくなるのではないかと思います。
また別記事は、学年毎に息子が取り組んだ学習内容と、全国統一小学生テストなどの模試についてまとめたいと思います。




